Hydrofoil ハイドロ フォイル
ハイドロ(Hydro)+フォイル(Foil)を組み合わせた名前で、Hydro:水に関する+Foil:翼のように、気流を利用して航空機を持ち上げたり制御したりすることを助けるために作られた薄片を示す。
水中翼船は、ボートに取り付けられる、フォイルは飛行機の翼のような形をしており、その上を水が素早く流れるように先細りになっている。高速になると、フォイル表面を流れる水流の作用で揚力が発生し、ボートは水面から空中に持ち上げられる。結果、抵抗が少なくなり、より速いスピードが出せるようになる。
通常のボートが前進するとき、そのエネルギーのほとんどは、ボートの前にある水を邪魔にならないように移動させるために費やされる(船体を押し流すことによって)。水中翼船は船体を水面から浮かせるので、船体にかかるすべての抵抗の代わりに、フォイルにかかる抵抗だけを考慮すればよい。
水中翼船の速度が上がると、水中翼船は、水中翼船が取り付けられている垂直の支柱に支えられて、完全に水面から離れるまで船体を上昇させる。さらに速度を上げると、水中翼船自体が水面から浮上し、その揚力がボートの重量分まで再び減少する。この作用表面積の自動的な減少を、ベルとボールドウィンは、帆になぞらえて「リーフィング」と呼んだ。水中翼船の角度によって水平力と垂直力の比が決まるため、水中翼船のリーフィングによって水平力(前進するための抵抗力)は速度が上がっても一定に保たれる傾向があるが、通常のボートでは抵抗力は速度の2乗に比例して増加する。
低速で水上を航行する際には船体を水面下に浸けて航行するが、高速航行をする際には、迎角のつけられた水中翼から得られる揚力で海面上に船体を持ち上がり、水中翼のみが水中に浸っている形になる。
構造と推進方式
水中翼船には構造や推進方式が様々あり、構造上の分類では、高速航行時に水中翼の一部が水面上に出る半没翼型水中翼船と、水中翼の全てが水面下にある全没翼型水中翼船とに大まかに分けられる。全没翼型水中翼船には、単胴型と双胴型がある。単胴型の全没翼型水中翼船の代表的なものにアメリカ・ボーイング社(日本では川重ジェイ・ピイ・エスがライセンスを取得した)の「ボーイング929 ジェットフォイル」がある。また、双胴型の全没翼型水中翼船には、三菱重工が開発した「スーパーシャトル400」があり、「レインボー2」が隠岐汽船に就航していた(2013年11月30日に退役)。
全没翼型は半没翼型と比較して安定性に劣るとされている。これは、「半没翼型の場合は特に水中翼の制御をしなくてもある程度の振動を伴いつつではあるが安定した浮上がなされるのに対し、全没翼型ではそのような自律的フィードバックが期待できないこと」「半没翼型に設けられている水中翼には大きな上反角が付けられ、横揺れに対する復原性が確保されていること」による。但し、近年ではコンピュータによる水中翼の能動的な制御技術が確立されたことにより、全没翼型でも安定性を確保できるようになっている。
全没翼型の安定性が確保されると、後述のような半没翼型のデメリットが浮き彫りになったこともあり、敢えて半没翼型を選択するユーザーが少なくなり、現在では全没翼型が主流となっている。
水中翼船の歴史
アレクサンダー・グラハム・ベルと水中翼船[1906年〜1921年]
電話の発明で有名なアレクサンダー・グラハム・ベルは、初期の航空機の研究をし、工学的な難題に取り組んでいた。
揚力を発生させるのに十分な速度を得るにはどうしたらよいか。
空中に飛び出したら、パイロットや飛行機を、どうやって安全に着陸させるか。
1902年、ベルは初期の凧の実験において、人間やエンジンを乗せられる大きさの凧をうまく揚げる方法を探した。このとき、工学的、数学的な問題が山積していた。凧を軌道に乗せて陸上で飛ばすか、浮きをつけて水上で飛ばすか。ベルは後者を選んだ。
ライト兄弟は、1903年のキティホークでの飛行の際(そしてその後数年間)、カタパルトシステムを使って飛行機を浮かせ、スキッドを使って着陸させた。
1906年までに、ベルはBeinn Bhreaghで水上実験用の四面体凧の実験に様々なタイプのフロートを使って実験していた。
ベルの研究所の管理者であったケイシー・ボールドウィンの船遊び好きが、晩年のベルの実験的興味に大きな変化を促したのかもしれない。1906年10月にベルが「水より軽い機械だけでなく、水より重い機械があってもいいじゃないか」と自問したとき、ボールドウィンはすでに数カ月間、この分野に携わっていたのである。ベルが言った「水より重い機械」というのは、このようなボートが、気球のように移動するのではなく、水中翼船(飛行機の翼のように水中で働く板または羽根)の揚力によって動けることを指している。このアイデアは、1861年にイギリスの運河、サリー運河でイギリスのエンジニア、トーマス・モイがボートにセットを取り付け、曳航実験に成功していた。船を牽引したときに「水からかなり」持ち上げられたと記している。
水中翼船のパイオニアであるアメリカのウィリアム・E・ミーチャムは、『サイエンティフィック・アメリカン』誌の1906年3月号の記事で水中翼の基本原理を解説し、自身の実験について発表した。
水中翼船のパイオニアであるアメリカのウィリアム・E・ミーチャムは、『サイエンティフィック・アメリカン』誌の1906年3月号の記事で水中翼の基本原理を解説し、自身の実験について発表した。
『サイエンティフィック・アメリカン』誌の1906年3月号の記事
HYDROPLANE BOATS
WILLIAM M. MEACHAM
Scientific American
Vol. 94, No. 9 (MARCH 3, 1906), pp. 188-189 (2 pages)
Published By: Scientific American, a division of Nature America, Inc.
ベルは、この基本原理を説明する記事を読んでいたのだろう。水中翼船の速度が上がると、水中翼船は、水中翼船が取り付けられている垂直の支柱に支えられて、完全に水面から離れるまで船体を上昇させる。さらに速度を上げると、水中翼船自体が水面から浮上し、その揚力がボートの重量分まで再び減少する。この作用表面積の自動的な減少を、ベルとボールドウィンは、帆になぞらえて「リーフィング」と呼んだ。水中翼船の角度によって水平力と垂直力の比が決まるため、水中翼船のリーフィングによって水平力(前進するための抵抗力)は速度が上がっても一定に保たれる傾向があるが、通常のボートでは抵抗力は速度の2乗に比例して増加する。
1906年、イタリアでは、エンリコ・フォルラニーニが水中翼船でマッジョーレ湖を横断するレースが目撃されている。
1907年9月30日にグラハム・ベルの指導のもとで、航空実験協会(Aerial Experiment Association:AEA)が設立された。カナダの航空の研究グループで1900年代後半に北アメリカで公開での飛行実験を行った。
サイグネット Cygnet
ベルが設計した、モーターを使わない有人凧で、蒸気船ブルーヒルの後ろに曳航された。1907年12月、セルフリッジ中尉を乗せ、バデック湾上空を8分間飛行。
レッドウィング Red Wing
セルフリッジが設計し、1908年3月にニューヨーク州ハモンズポートでボールドウィンが飛行させた。
ホワイト・ウィング White Wing
ボールドウィンが設計。北米で初めて三輪車の足回りを装備。
ジューンバグ June Bug
カーチスのデザイン。1908年7月4日、サイエンティフィック・アメリカン・トロフィーを受賞、北米初の一般向け飛行となる
シルバーダート Silver Dart
マッカーディが設計し、1909年2月にカナダで初飛行。
ドローム5号 Drome #5(愛称:シグネットII Cygnet II)
モーター付きの四面体カイト。飛行には失敗した。
ドローム6号 Drome #6 (ドンナス・ビーグ Dhonnas Beag)
ボートと飛行機械の複合機として計画された。ボールドウィンはこのプロジェクトの責任者であった。
ボートと飛行機械の複合機として計画された。ボールドウィンはこのプロジェクトの責任者であった。
AEAの仕事は、ニューヨーク州ハモンズポートにあるグレン・カーティスの機械工場と、ベルのベイン・ブレアグ研究所で行わた。
1908年6月、AEAの一部のメンバーがニューヨークでJune Bugの最終調整に取り組んでいる間、ベルとBeinn Bhreagh研究所は彼の四面体凧のために双胴船発射機The Getawayを製作させた。
1908年11月、成功したJune Bugに双胴船型のフロートと水上飛行機を装備することを決定する。ボールドウィンは船乗りとしての専門知識を生かし、水上飛行機を設計することにした。しかし、ハモンズポート本社近くのケウカ湖からの離陸はうまくいかなかった。
ベル&ボールドウィン社にとって、水中翼船の実験は、離着陸に関する問題を克服しようとし続けた、飛行機の開発における自然な流れとして行われたのである。このように水中翼船の開発は、AEAの航空関係の仕事と直結しており、その直接的な成果でもあった。
ベルとボールドウィンが水中翼船の実験を始めたのは1908年の夏で、その時も単に水中翼船の原理が水上からの航空機の離陸方法に使えるのではないかと考え、実験を開始した。
しかし、ボールドウィンがイタリアの発明家エンリコ・フォルラニーニのの業績を研究し、模型をテストし始めると、彼とベルも水中翼船に目を向けるようになり、軍用の水中翼船の実用化に向かうことになった。ベルの関心は活発で、提案も鋭かった。その年の秋も曳航試験は続いたが、ストレスで部品が故障するなどのトラブルが続いた。しかし、ボールドウィンが乗った2隻の曳航式水中翼船は、船体が水面から浮き上がった。また、ボールドウィンは、水中翼の下端と上端が水平になるように傾斜した梯子状の水中翼のセットを設計し、リーフィング動作を跳ね上げるのではなく、連続させるようにした。
しかし、ボールドウィンがイタリアの発明家エンリコ・フォルラニーニのの業績を研究し、模型をテストし始めると、彼とベルも水中翼船に目を向けるようになり、軍用の水中翼船の実用化に向かうことになった。ベルの関心は活発で、提案も鋭かった。その年の秋も曳航試験は続いたが、ストレスで部品が故障するなどのトラブルが続いた。しかし、ボールドウィンが乗った2隻の曳航式水中翼船は、船体が水面から浮き上がった。また、ボールドウィンは、水中翼の下端と上端が水平になるように傾斜した梯子状の水中翼のセットを設計し、リーフィング動作を跳ね上げるのではなく、連続させるようにした。
水中翼船を応用した別の船のテストは、1909年の夏の終わりと秋に行われた。
1908年10月のAEA 広報誌で、ベルはこれを「ボールドウィンのハイドロ・アエロドローム:Baldwin’s hydro-aerodrome」と呼び、「ボート本体の下に水中飛行機を配置して上昇を助ける」計画であったという。 彼はこう続けた。
「水鳥のように水に浮かび、水から上昇することができるように、その本体はアウトリガーを備えたボートの形でなければならない」。
ボールドウィンは、これを「ボート、水上飛行機、飛行機の三位一体」と呼んだ。
この試みは、水面から上昇するエンジンを作るための予備的なものであった。
AEAのメンバーであるベル、マッカーディ、ボールドウィン、セルフリッジはそのころできたばかりのブラスドール・ヨットクラブに入会した。 会員となり、クラブの初期のレースの運営を手伝った。 1908年のある会合で、ベルはクラブの幹事に呼ばれ、ヨットやレースについて話している。幹事は、ベルが次のように主張したと記している。第一に安全、第二に快適、第三にスピード」。 また、「プロペラが空中にあるボートはモーターボート・レースに参加する資格がある」とも述べている。1909年のAEA終了後、ベル、ボールドウィン、マッカーディは、カナダに航空産業を興すべく、カナダ飛行場会社(CAC)を設立する。同社は航空機の製造と試験を行うが、航空機の注文がなく、1年後に事業をたたむ。
1910年から1911年にかけてベル&ボールドウィン夫妻は世界旅行に赴き、この新しい実験が中断されたが、その間にベルとボールドウィンはイタリアでフォルラニーニと面会し、マッジョーレ湖でフォルラニーニの水中翼船に乗った。「父もケイシーも急行列車の速度でマッジョーレ湖の上を走る(フォルラニーニの水中翼船に)乗った」と、1911年の春に(ベルの妻)メイベルから娘のエルシーに書いている。「二人はその感覚を、最も素晴らしく、楽しいものだと表現した。ケイシーは、まるで空を飛んでいるような滑らかさだと言っていました。船は......時速約45マイルで水の上を滑るように進み......ほとんど波紋を残さない細い水中飛行機で支えられているのです」。AEAのメンバーであるベル、マッカーディ、ボールドウィン、セルフリッジはそのころできたばかりのブラスドール・ヨットクラブに入会した。 会員となり、クラブの初期のレースの運営を手伝った。 1908年のある会合で、ベルはクラブの幹事に呼ばれ、ヨットやレースについて話している。幹事は、ベルが次のように主張したと記している。第一に安全、第二に快適、第三にスピード」。 また、「プロペラが空中にあるボートはモーターボート・レースに参加する資格がある」とも述べている。1909年のAEA終了後、ベル、ボールドウィン、マッカーディは、カナダに航空産業を興すべく、カナダ飛行場会社(CAC)を設立する。同社は航空機の製造と試験を行うが、航空機の注文がなく、1年後に事業をたたむ。
1911年の夏の終わりにベルとボールドウィンがバデックに戻ったベルとボールドウィンは、水中翼船に再び情熱をかたむけた。ボールドウィンは水中翼船を設計・製作し、ベルとともに「ハイドロドーム」と呼び、HD-1と命名した。その空中プロペラと揚力増強のための短い複葉翼は、その秋に無造作に離陸して湖面を滑走する発育不良の水上飛行機のように見えた。冬の間に再設計され、1912年7月から10月にかけて再度テストが行われ、原因不明の亀裂が入る前に時速50マイルを記録した。HD-2型に改修されたが、この速度記録には及ばず、12月に構造上の欠陥で使用不能となった。
一方、1912年9月、ベルは水中翼船に魅惑的なイメージを抱いていた。しかし、船乗りであるボールドウィン(Baldwin)は、水中翼船で船体を水面上に浮かせるためには、最も速い帆船でもその速度に遠く及ばないと指摘した。ベルは、水平帆による空力的な揚力を加えることを提案しただけで、大型客船が風の翼に乗って大西洋を無煙で滑走する夢を見るに至った。そこで1913年の夏、ケイシーはベルと一緒にひたすらテストモデルを作った。
1913年初め、ボールドウィンはベルの勧めでHD-3を設計、製造した。これは、もう一つのずんぐりした小さな準航空機である。バディエック湾に入港したモナコ王子のために行ったデモンストレーションで、構造上の欠陥から亀のように回転してしまったのが最大の見せ場だった。1914年にこの船を稼働させることは、ベルの水中翼船構想のさらなるテストに多くの時間と資金を割くことになるとケイシーは考えたのである。
水中翼船の夢は、2度目の夏の実りのない試験の後、1914年に終わったが、その年の8月にヨーロッパ戦争が勃発し、水中翼船モラトリアムは2年延長された。ボールドウィンは、ハイドロドロームが実現するような高価なプロジェクトに民間の資金を提供することはできないし、戦時中の政府もそうすることはできないと考えた。ベルは、中立国の国民として、海軍に利用されるかもしれない実験をカナダで行うべきではないと判断した。そこで、労働者の雇用を守るために、ケイシーに実験施設を使わせて、地元の人々や夏の住民のために小舟を作らせた。
1915年、ベルはボールドウィン社製のHD-3をアメリカ海軍に売り込むことに失敗していた。彼の望みは、アメリカの参戦後、海軍省が潜水艦追跡機の製造提案を募集したときによみがえった。そのために水中翼船を2隻作ることを提案し、ベルとボールドウィンは嬉々として古い曳航試験の記録を調べ、新しい設計を議論した。ベルは「爆弾のようにキャンプに落ちてきて、私たちの計画はすべて打ち砕かれた」と記録している。しかし、メイベルはとにかくお金を出すと言い、ベルは海軍に400馬力のリバティエンジン2基の貸与を約束させた。そして、HD-4の設計が再開された。HD-4は、前任者の成功や失敗から学んだことをすべて盛り込んだ。全長6フィートの葉巻型の船体に、前方に2組、後方に1組のリーフィング付き水中翼船を乗せた、なめらかなグレーの巨人である。両側には、流線型のアウトリガーに取り付けられた小さな船体があり、静止状態で浮遊しているときにバランスをとるようになっていた。アウトリガーにはモーターとプロペラが搭載されていた。その後、左右のスプレーシールドはアウトリガー船体から機首に向かって細くなり、翼のある外観になり、実際、空気力学的な揚力にも貢献している。海軍は約束のリバティエンジンを用意することができず、また用意しようとせず、送られてきた2台の25馬力ルノーエンジンさえも1918年7月まで到着しなかった。(HDはHope Deferredの略だとの説もある)そのため、最初の試運転が始まったのは1918年10月になってからである。
ルノー・エンジンの場合、最高速度は時速87km/hにとどまった。しかし、HD-4は、上昇しやすく、加速しやすく、波にも乗りやすく、操舵性もよく、安定性も高いという優れた性能を発揮した。1919年初頭、ベルが海軍に提出した報告に加え、戦後リバティエンジンが入手可能になったこともあり、海軍はついに1919年7月に350馬力のリバティ2機を提供するに至った。この2基の空中プロペラを動力源とするHD-4は、1919年9月9日にバデック湾で当時の水上船舶の世界最高速度記録である時速114.0キロを達成し、この記録は10年間破られることがなかった。
その光景は爽快で、実際に乗ってみるともっと爽快だった。「15ノットの速度で、マシンが水面から勢いよく立ち上がるのを感じる」とある見学者は書き、「いったん立ち上がって抵抗がなくなると、取り残されないように座席を握りしめるほどの加速度で走り出す。顔に当たる風は巨大な手の圧力のようで、時折細かいしぶきが鳥銃のように刺さる。. . . 曲がるとき、彼女は一度もヒールしていないようだ。信じられない。物理学の法則に反しているが、本当なんだ」。ベル自身は、この船に乗ることはなかった。
1919年のテストに続いて、カナダ海軍の標的を曳航する実験的なハイドロドロームがさらに製造・テストされる。Bell & Baldwinは会社を設立し、特許を取得する。
1919年のテストに続いて、カナダ海軍の標的を曳航する実験的なハイドロドロームがさらに製造・テストされる。Bell & Baldwinは会社を設立し、特許を取得する。
1年後、ベルはイギリス海軍とアメリカ海軍から、デモンストレーションを見るためのオブザーバーを得ることに成功した。両者とも熱心な報告をしてくれた。しかし、長い間先延ばしにしてきたが、どちらの海軍も発注する気になれなかった。アメリカ海軍は、このような船は海上で行動するにはもろすぎると考え、水上機とモーターボートの組み合わせの方が好ましいと考えた。1921年の海軍軍縮会議は、イギリスの関心を低下させた。1921年秋[ベルが75歳で亡くなる1年前]、HD-4は解体された。その大きな灰色の船体は、Beinn Bhreahの海岸に何十年も放置されたままであった。
ベル以降の水中翼船開発
ケイシー・ボールドウィンは、水中翼船モーターボート、曳航目標物、海上テスト用発煙装置の設計と製造を続けている。後年、ボールドウィンはノバスコシア州議会議員になり、ケープブレトン北部のケープブレトン高地国立公園の開発を奨励する。
1950年代から1960年代にかけて、カナダ海軍は実験的な海軍用水中翼船の開発を開始した。
KC-B(別名マサウィッピ号) ケベック州で製造され、ハリファックス港でテストされた14m、5トンの実験船。
R-103(Brasd'Orとして進水、Baddeckと改名) 連邦国防省の国防研究委員会の委託を受け、ウェールズの英国企業サンダース・ロー社で建造された。
Bras d'Or:カナダ海軍の軍艦で水中翼船を装備、海上試運転を行い水中翼船で時速112キロを記録。
最初の旅客船
ドイツ人技師ハンス・フォン・シェルテルは、第二次世界大戦前から大戦中にかけてドイツで水中翼船の研究を行っていた。戦後、ロシア軍がシェルテルのチームを捕らえた。ドイツは高速船を建造する権限を与えられていなかったため、シェルテルはスイスに渡り、1952年にシュプラマール(Supramar)社を設立した。創業以来1971年まで、多くのモデルの旅客用水中翼船を設計した。
1952年、スイスとイタリアの間にあるマッジョーレ湖で、PT10「フレッチャ・ドーロ」(ゴールデンアロー・金の矢)という水中翼船を初めて商業的に売り出した。PT10は水中翼船で、乗客32人を乗せ、35ノット(時速65km)の速度で走行することができた。
1953年5月、イタリアのマッジョーレ湖で世界初の旅客水中翼船サービスが開始され、PT10が就航した。1953年には、より大型のPT20がリュルセン造船所Lürssenで建造され、ブレーメンのパイオニアBremen Pioneerと命名された。シュプラマール社は200機以上製造したが、その後、Supramarのライセンスにより、そのほとんどはイタリアのシチリア島にあるロドリゲス社Rodriquezで製造された。日本の日立造船はライセンス供与を受け、 1962 年よりPT20 と PT50 型をライセンス生産した。ノルウェーのウェスターモーンWestermoenによって多くのSupramar型水中翼船が建造され、現在も多くのSupramar PT 20とPT 50水中翼船が就航している。
1968年、バーレーン生まれの銀行家フセイン・ナジャディがシュプラマール社を買収し、日本、香港、シンガポール、英国、ノルウェー、米国に事業を拡大した。米国のゼネラルダイナミクス社がライセンス提供を受け、米国防総省からスーパーキャビテーション分野での初の海軍研究開発プロジェクトを受注した。OECD諸国の主要な船主や造船所もライセンスを取得した。
1953年5月、イタリアのマッジョーレ湖で世界初の旅客水中翼船サービスが開始され、PT10が就航した。1953年には、より大型のPT20がリュルセン造船所Lürssenで建造され、ブレーメンのパイオニアBremen Pioneerと命名された。シュプラマール社は200機以上製造したが、その後、Supramarのライセンスにより、そのほとんどはイタリアのシチリア島にあるロドリゲス社Rodriquezで製造された。日本の日立造船はライセンス供与を受け、 1962 年よりPT20 と PT50 型をライセンス生産した。ノルウェーのウェスターモーンWestermoenによって多くのSupramar型水中翼船が建造され、現在も多くのSupramar PT 20とPT 50水中翼船が就航している。
1968年、バーレーン生まれの銀行家フセイン・ナジャディがシュプラマール社を買収し、日本、香港、シンガポール、英国、ノルウェー、米国に事業を拡大した。米国のゼネラルダイナミクス社がライセンス提供を受け、米国防総省からスーパーキャビテーション分野での初の海軍研究開発プロジェクトを受注した。OECD諸国の主要な船主や造船所もライセンスを取得した。
シュプラマール(Supramar)社の開発したシリーズ
水中翼船 1961年(昭和36年)日立造船で新造船された水中翼船の広告
- PT-10, 商業用水中翼船第1号 1952年
- PT-20 MKII, 商業用水中翼船の最初のシリーズ
- PT-50 MKII, エアフィードフォイルによるスタビライジングを特徴とする最初の船
- PT-75 MKIII, スタビライジングシステムを搭載した最新鋭の内航船
- PT-150 MKII, スタビライジングシステムを搭載したシリーズ最大の船
- MT-250, 軍用プロジェクト
水中翼船 1961年(昭和36年)日立造船で新造船された水中翼船の広告
同時期のソビエトでは水中翼船の実験が盛んに行われ、冷戦期から1980年代にかけて流線型の水中翼船やフェリーが建造された。1950年代の高速水中翼船の設計にソビエトの設計者/発明家のロスチスラフ・アレクセイエフ(Rostislav Alexeyev)が貢献していた。アレクセイエフは当初、戦車製造の現場監督を務めていたが、1942年にソ連海軍から戦闘用の水中翼船の開発に再配属された。彼の設計は1945年の終戦までに完成しなかったが、ソ連政府の関心は高く、1940年代末には340隻の水中翼船が計画されていた。アレクセイエフは水中翼船の研究を続け、1957年に生産を開始したソ連初の商業用旅客水中翼船「ラケータRaketa (ロケット)」の主任設計者になった。この年、モスクワで開催された「国際青年学生フェスティバル」でラケタが発表され、水中翼船への関心がさらに高まった。アレクセイエフは、レッド・ソルモヴォKrasnoye Sormovo社で生産された「メテオールMeteor(流星)」「コメータKometa(彗星)」「スプートニクSputnik (衛星)」「ブレベストニクBurevestnik(海燕)」「ボスホートVoskhod (日の出)」など、数多くの旅客用水中翼船の設計主任を務めた。その後、1970年代頃には水中翼船の経験を表面効果原理と組み合わせてエクラノプランを作り上げた。ソビエトにおけるこの種の技術への大規模な投資は、世界最大の民間水中翼船群や、400台以上が製造された歴史上最も成功した水中翼船である「メテオール(流星)」の製造につながった。
ボスホート(日の出)は、ソビエト、後にウクライナのクリミアで製造された。河川や湖沼での使用を意図しているが、耐航性が良好で沿岸海域でも操業できる。20カ国以上で使用されており、最新のモデルであるVoskhod-2M FFFは、ユーロフォイルとも呼ばれ、オランダの公共交通機関事業者コネクシオン(Connexxion)のためにフェオドシヤで製造された。
米国における水中翼船の商業利用は、1961年にノースアメリカン・ハイドロフォイル社がニュージャージー州のアトランティックハイランドからロウアーマンハッタンの金融街へのルートを運航するため、コミュータ船2隻の委託を受けたものが初めてであった。
新明和工業は飛行艇を製造した経験と知識を生かして1961年に「SF-30」(約15人乗)を開発した 。前中後の3つの水中翼を持ち、艇走時には跳ね上げられる。船体は軽合金を使用し、表面にプラスチックコーティングを施し、普通の船と比べて補修費も安く耐用年数も2倍近くあった。1962年3月に野母商船が開業した日本初の水中翼船の定期航路である長崎・時津港~佐世保を結ぶ路線に使用されたが、2年足らずで廃止された 。
三菱造船は当初グラマンやボーイング社との技術提携も考えていたが、条件が折り合わず自主開発の道を歩んだ 。米海軍が水中翼船の開発が活発化していたこともあり、魚雷艇を製造していた三菱は軍用に開発を進めてきた。その後商用艇への期待が高まってきたため1961年に5人乗りのMH-1と12人乗りのMH-3を開発した。1963年には80人乗りのMH-30を開発した。MH-30は近鉄志摩観光汽船で「Pearl Queen」と名付けられ、運航された。名古屋-鳥羽間で運行した。当時、ライバル関係にあった名鉄観光もPT-20とPT-50で名古屋-鳥羽間を就航させており水中翼船同士の対決となっていた。1976 年 10 月 1 日を以てその水中翼船運航は打切りに至った。
深日海運(ふけかいうん)1994年9月4日に社名をえあぽーとあわじあくあらいんに変更
1993年11月10日 - 高速船「とらいでんとえーす」就航。以後「あるてみす」「あぽろーん」順次就航。
実験終了後、神戸海洋博物館で展示されていた「疾風(はやて)」
2016年11月に解体撤去された
1990年代にIHI、川崎重工、住友重機械工業、日本鋼管、日立造船、三井造船、三菱重工の7社でテクノスーパーライナー(TSL)と呼ばれる高速・大量輸送を実現できる船の開発が行われた 。目標は速度50ノット、貨物積載重量1000トン、航続距離500海里とし、研究段階では2つの試験船が作られた。1つは浮力と揚力で航行する揚力式複合支持型(TSL-F船型)「疾風(はやて)」で、もう1つは浮力と空気圧で航行する空気圧力式複合支持型(TSL-A船型)「飛翔」である 。
疾風(はやて)は実用船の1/6スケールの試験船で、上部船体はアルミ合金で、水中にある下部船体はステンレス鋼でできている。ジェットフォイルとは違い、全重量の半分を下部船体の揚力で支持し、残りの半分は浮力で支持している 。波高6mでも航行できることを目標に設計された。浮力で支持しているが、構造上自己復元力はほとんど働かない。そのため姿勢制御システムが非常に重要であり、疾風はこのシステムを実海域において試験するために作られた。1989年から1992年にかけて開発・設計・製造され、1992年から1994年にかけて試験航行が行われた。試験は主に大阪湾で行われた。高さ6mの波でも40ノットの速度で安定して航行でき、優れた耐航性と操縦性を確認した。また実船を建造するための設計技術があることも実証した。しかし船価や維持費が高く、TSL-F船型の実用化は見送られた。
出典:
Hydrofoil - Wikipedia
近代的な旅客水中翼船
ボーイング929(Boeing 929 Jetfoil)
ボーイング929ジェットフォイルは、ボーイング社による乗客定員制のウォータージェット推進型水中翼船である。
.jpg=rw)
.jpg=rw)
The jetfoil Toppy 3 glides into Miyanoura on the northeast
side of Yakushima Island, Japan.
side of Yakushima Island, Japan.
19 October 2016
David Stanley from Nanaimo, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
「ジェット」は本船がジェットエンジンとウォータージェット推進機によって駆動されることからきており、「フォイル」とは、「鋭い薄い翼」を表わす英語に由来する。
ボーイング社は、ジェット機で使われている多くのシステムを水中翼船に応用した。ロバート・ベイトマンが開発を主導した。1974年4月、ボーイング社は初の旅客機用ウォータージェット推進水中翼船を発表した。167人から400人の乗客を乗せることができた。米海軍の哨戒用水中翼船「トゥカムカリ」用に開発された技術をベースに、ペガサス級軍用哨戒水中翼船と技術を共有したものである。
速度: 約45ノット(時速約83km)
航続距離: 約450km
船体材料: アルミニウム合金
全長: 27.4m
水線長: 23.93m
全幅: 8.53m
吃水: 5.40m(艇走状態でストラットを完全に下げた時)
吃水: 1.83m(艇走状態でストラットを完全に上げた時)
型深さ: 2.59m
総トン数: 267トン
純トン数: 97-98トン
旅客定員: 約260名
機関: アリソン501-KF ガスタービン×2基(2767kW×2)
推進器: ロックウェルR10-0002-501 ウォータージェット×2基
ボーイング社の設計製造であるが、現在はライセンスを引き継いだ川崎重工業の登録商標となっており、 製造・販売権を得た川崎重工業が、この名前を引き継いでおり、現在は「川崎ジェットフォイル929-117型」として、製造・販売を行なっている。
日本の多くの島々の間、香港とマカオの間など、アジアで広く使用されている。ボーイング社は、1975年に買収したジェットフォイル929-100水中翼船3機をハワイ諸島で運航するために発売し、ホノルルに拠点を置く運航会社シーフライトが運航していた。Seaflite社は1975年から1979年にかけて、3機のボーイング929-100ジェットフォイルを運航していました。香港-マカオ間を運航するため、3機のジェットフォイルはファーイーストハイドロフォイル(現ターボジェット)に買収されました。約24機のボーイングジェットフォイルは、香港-マカオ、日本、韓国、イギリス海峡、カナリー諸島、韓国海峡、サウジアラビアとインドネシアで運航されました。
1977年に日本でこの旅客用が初導入された。日本国内ではジェットフォイル (Jetfoil) という愛称を持つ。
1979年、イギリス海軍はボーイング・ジェットフォイル、HMSスピーディを購入し、現代的な水中翼船の運用とサポートの実践的な経験を積む機会を与え、技術・性能特性を確立し、漁業保護飛行隊における水中翼船の能力を評価するために使用した。
1980年、B&IシッピングラインズはジェットフォイルCú Na Mara (Hound of the Sea)を使ってダブリンからリバプールへのジェットフォイルサービスを開始した。このサービスは成功せず、1981年のシーズン終了後に廃止された。
ベルギーのRegie voor Maritiem Transport (RMT) は、1981年から1997年まで、オステンド-ドーバー間でジェットフォイルプリンセス・クレメンタインとプリンセス・ステファニーを運航していた。
北米では、1980年の夏の観光シーズンに、ボーイング社のジェットフォイルがワシントン州シアトルとブリティッシュコロンビア州ビクトリアを結ぶ定期便として運航されました。ボーイング社からリースされたジェットフォイル1機「フライング・プリンセス」は、BCスチームシップ社の密接な協力と援助のもと、非営利団体「フライング・プリンセス輸送社」によって運航された。1985年4月から9月までシアトル~ビクトリア~バンクーバー間で、アイランドジェットフォイルによる定期便運航が行われた。ボーイング社はアイランドジェットフォイルの船を再生し、日本での運航のために売却した。
1959年、ボーイング社は水中翼船の研究開発を開始した。1961年にはボーイング社の「アクアジェット」と呼ばれる流体力学試験装置(HTS)が発売されました。これは、水上版風洞の役割を果たす、2人乗りのジェットエンジン搭載の水上飛行機でした。アリソンJ-33ジェットエンジンを搭載したHTSは、132ノット(115mph/185kph)までの直線飛行に適した水平で安定したプラットフォームを提供するように設計されていました。2本のプロウの間に取り付けられた制御可能な固定具が、試験航行中に水中翼船の模型を水中に保持しました。
1962年、ボーイング社は社費研究船として、ボーイング社製520型タービンエンジンを搭載したリトル・スクワートを製作した。後部のフォイルに内蔵されたスクープから水をくみ上げ、ノズルから船体後方の空中に放出する。全長6mの「リトル・スクワート」は、フォイルの深さ、速度、荒海での動作、ゴミの中での動作などの情報を提供する。リトル・スクワートは、安定性と制御のための可動面を持つ完全潜水式フォイルを持っていた。これらの表面は、ボートの水面からの高さ、ピッチ、ロール、ヒーブを感知し制御する先駆的な自動制御システムに接続されていた。
ボーイング社のモデル883、FRESH-1(foil research experimental supercavitating hydrofoil)は、米海軍の水中翼船研究の一環であった。ボーイング社がFRESH-1を設計したのは、キャビテーションと呼ばれる現象を調べるためである。高速回転時には「ベーパーキャビティ」と呼ばれる空洞や気泡ができ、効率の低下や不安定な運転が発生することがある。そこで、キャビテーションが発生する速度以上の速度で航行できるよう、ホイルシステムが設計された。
1963年、FRESH-1は84ノット(時速96マイル/155キロ)を達成し、1919年にアレクサンダー・グラハム・ベルが樹立した長年の記録を塗り替えた。この時、墜落事故が発生したため、海軍は100ノット(時速185km)のホイルシステムの試験を行わないことを決定した。
PCH-1(「巡視船水中翼船」)ハイポイントは、アメリカ海軍の最初の運用水中翼船であり、ボーイング水中翼船ファミリーの最初の船である。全長117フィート(35メートル)のハイ・ポイントは、主に対潜水艦戦のコンセプトの研究と開発に使用されました。1962年8月17日に進水し、1963年から1967年までピュージェット湾でテストされました。2基のガスタービンエンジンで4つのプロペラを駆動し、50ノット(時速57マイル/92キロ)の速度を出すことが可能でした。1975年にアメリカ沿岸警備隊に移管され評価されましたが、吹き飛んだエンジンを交換する資金がなかったため、海軍に返還され退役しました。
ボーイング923型、PGH-2(「巡視砲艦水中翼船」)トゥーカムカリは、1967年に進水した。57.5トン(58.4トン)、全長74.6フィート(22.7メートル)の船体はアルミニウム製で、フォイルと支柱は耐食鋼製であった。ウォータージェット推進システムを採用し、3,200馬力のロールス・ロイス社製タービンエンジンを搭載していました。
トゥーカムカリはアメリカ海軍のベトナム戦争に参加しました。その後、1970年8月に大西洋に配属され、NATO8カ国でその能力を発揮しました。1972年11月、カリブ海で夜間フォイルボーン運用中、トゥーカムカリは座礁しました。乗員に大きな怪我はなかったが、岩礁からの撤去作業中に再び航行できないほどの損傷を受け、海軍の現役艦艇の記録から抹消されることになった。
イタリアはトゥーカムカリをベースにボーイング社設計のスパルビエロ級6隻を建造し、パトロール水中翼船(PHM)計画が発足した。武装水中翼船は、米国、ドイツ、イタリアとのNATO共同プログラムのもとで開発された。最初のPHM(ボーイング社製モデル928)は、1974年11月に進水したUSSペガサス(PHM-1)である。ボーイング社製としては初めて、また水中翼船としても初めて、米国船籍(USS)に指定されました。
1975年、シアトルからサンディエゴまでの1,225マイル(1971キロ)を34時間(給油のため1回停泊)という記録的な速さで航行しました。1977年7月9日に就役した。1981年から1982年にかけて、ワシントン州レントンのボーイング社工場でさらに5隻のペガサス級艦艇(ヘラクレス、タウルス、アクィラ、アリエス、ジェミニ)が建造された。
76mm速射砲とAGM-84ハープーン対艦ミサイル8基を搭載し、より大型の軍艦に対抗することができた。5日以上の自給自足が可能で、航行中に燃料を補給できるため、輸送船の護衛や空母の戦闘団の一員として活躍したが、フロリダ州キーウエストを拠点として、密輸業者や麻薬密売人の取り締まりが主な任務であった。1993年、政府の削減策によりPHMは退役した。
ボーイング社は商業用水中翼船も製造していた。1972年、理事会はジェットフォイル・プログラムにゴーサインを出した。ボーイング・ジェットフォイル(ボーイング・モデル929)は、高速での乗客の快適さを追求したものであった。ジェットフォイルは、高速での快適な乗り心地を追求したもので、3本の細い支柱が生み出す航跡は、同規模の船が作る航跡の何分の1かであった。また、音も従来のオートフェリーと同じように静かである。停止距離は152メートル、旋回半径は196メートルで、混雑した水路でも簡単に操ることができる。
標準的な乗客定員は250人だが、設計の柔軟性により最大350人まで乗れるバリエーションがある。アリソン・ガスタービンエンジンを2基搭載し、ロケットダイン社のウォータージェットポンプを駆動させ、115トン(104.32トン)の船を45ノット(時速51.8マイル)以上の速度で推進させることが可能であった。ボーイング社は、香港、日本、英仏海峡、カナリア諸島、サウジアラビア、インドネシアで使用するために、ワシントン州ボーイング・レントン工場で24隻のジェットフォイルを製造した。
日本国内を結ぶ航路
航路
新潟 - 両津
船名 : ぎんが、つばさ、すいせい
運航会社 : 佐渡汽船
東京(竹芝旅客ターミナル) - 久里浜 / 館山 - 伊豆大島 - 利島 - 新島 - 式根島 - 神津島
船名 :セブンアイランド愛、友、大漁、結
運航会社 : 東海汽船
熱海 - 伊東/稲取 - 伊豆大島(元町/岡田)
船名:セブンアイランド愛、友、大漁、結
運航会社 : 東海汽船
松江(七類) - 隠岐・島後島(西郷) - 中ノ島(菱浦) - 西ノ島(別府)
船名愛称 : レインボージェット
運行会社 : 隠岐汽船
博多(博多ふ頭) - 壱岐(郷ノ浦 / 芦辺) - 対馬(厳原) - 対馬(比田勝)
船名 : ヴィーナス、ヴィーナス2
運航会社 : 九州郵船
長崎 - 中通島(奈良尾) - 福江島(福江)
船名 : ぺがさす、ぺがさす2
運航会社 : 九州商船
鹿児島(本港区南埠頭) - 指宿 - 種子島(西之表)・屋久島(宮之浦 / 安房)
船名愛称 : トッピー、ロケット
運航会社 : 種子屋久高速船
日本での水中翼船 開発と製造
水中翼船の技術開発が本格的にスタートしたのは1960年ごろで、三菱造船や新明和工業は独自開発を目指し、日立造船はシュプラマール社との技術提携によって開発を進めた。新明和工業は飛行艇を製造した経験と知識を生かして1961年に「SF-30」(約15人乗)を開発した 。前中後の3つの水中翼を持ち、艇走時には跳ね上げられる。船体は軽合金を使用し、表面にプラスチックコーティングを施し、普通の船と比べて補修費も安く耐用年数も2倍近くあった。1962年3月に野母商船が開業した日本初の水中翼船の定期航路である長崎・時津港~佐世保を結ぶ路線に使用されたが、2年足らずで廃止された 。
三菱造船は当初グラマンやボーイング社との技術提携も考えていたが、条件が折り合わず自主開発の道を歩んだ 。米海軍が水中翼船の開発が活発化していたこともあり、魚雷艇を製造していた三菱は軍用に開発を進めてきた。その後商用艇への期待が高まってきたため1961年に5人乗りのMH-1と12人乗りのMH-3を開発した。1963年には80人乗りのMH-30を開発した。MH-30は近鉄志摩観光汽船で「Pearl Queen」と名付けられ、運航された。名古屋-鳥羽間で運行した。当時、ライバル関係にあった名鉄観光もPT-20とPT-50で名古屋-鳥羽間を就航させており水中翼船同士の対決となっていた。1976 年 10 月 1 日を以てその水中翼船運航は打切りに至った。
1993年に全没型水中翼船「スーパーシャトル400」を開発した。双胴船の船底に水中翼を設置し、ジェットフォイルと同じように船体全てを水面上に出して航行する 。双胴船とすることで水中翼を大型化し、波が船底に当たったときの衝撃を緩和できる。さらに座席を横に16列並べられ客室を広くできるので居住性が向上している。しかし水中翼を跳ね上げられないので、喫水を浅くするためにストラットを長くすることは難しかった。ジェットフォイルと同様に徹底した軽量化が図られ、外板の板厚を薄くしハニカム構造を採用している。エンジンは2850馬力の4サイクル・2000rpmのディーゼルエンジンを4機搭載している 。ディーゼルエンジンは給排気装置や補機類が多くガスタービンと比べて重たいが、水中翼を大型化することで性能を補っている。ジェットフォイルと同様に姿勢制御装置を搭載しておりAPF(Auto Pilot on the Foils)の名前がついている。定員は341名で時速74kmで航行する。センサー類はジェットフォイルより少なく効率化されている。載貨重量トン数は35トンで、航続距離は800kmになる。隠岐汽船で2隻使用されていたが2013年に引退し、1隻は韓国の大亜高速海運で2018年まで使用されていた。当初は200人乗りのスーパーシャトル200も開発する予定であったが、400の販売実績を受けて中止された。
日立造船は1960~80年にかけてスイス・シュプラマール社の半没型水中翼船を日立-PT20,50型という名前でライセンス生産していた。およそ50隻ほどの水中翼船を生産し、これらは瀬戸内海を中心に運航された。代表的な運航会社として、瀬戸内海汽船、石崎汽船、阪急汽船、名鉄海上観光船等がある。また東海汽船による東京湾横断航路でも使われていたため首都圏でも見ることができた。
プロペラ駆動で時速64kmの速度を出せたが、水面上に翼が出ているので波の影響を受けやすかった。しかし左右に傾いたときに元の姿勢に戻ろうとするので、高度な姿勢制御システムを必要としない。そのためジェットフォイルより安価で構造が簡単であった。しかし、低燃費で高速航行が可能な反面、波の影響を受け乗り心地が悪い上に維持コストが高く、水中翼の接触を防ぐ専用の接岸施設のない港に入港することができない等の欠点があり、次第に他の高速船やジェットフォイルにシェアを奪われていった。
日立造船は1960~80年にかけてスイス・シュプラマール社の半没型水中翼船を日立-PT20,50型という名前でライセンス生産していた。およそ50隻ほどの水中翼船を生産し、これらは瀬戸内海を中心に運航された。代表的な運航会社として、瀬戸内海汽船、石崎汽船、阪急汽船、名鉄海上観光船等がある。また東海汽船による東京湾横断航路でも使われていたため首都圏でも見ることができた。
プロペラ駆動で時速64kmの速度を出せたが、水面上に翼が出ているので波の影響を受けやすかった。しかし左右に傾いたときに元の姿勢に戻ろうとするので、高度な姿勢制御システムを必要としない。そのためジェットフォイルより安価で構造が簡単であった。しかし、低燃費で高速航行が可能な反面、波の影響を受け乗り心地が悪い上に維持コストが高く、水中翼の接触を防ぐ専用の接岸施設のない港に入港することができない等の欠点があり、次第に他の高速船やジェットフォイルにシェアを奪われていった。
1999年5月9日、石崎汽船の松山~尾道航路の最終運航を以って、半没型水中翼船は国内定期航路から姿を消した。
双胴水中翼船スーパージェットの開発(1986-1993)
Development of Hydrofoil Catamaran(SUPER JET)
スーパージェットは、東京大学、日立造船、瀬戸内クラフトが共同開発したハイブリッド船型の双胴水中翼船。基本型のスーパージェット30(SUPER JET-30)が8隻、拡大型のスーパージェット40(SUPER JET-40)が1隻の合計9隻が建造された。船体の浮力と全没型水中翼を併用して浮上航行するハイブリッド船型の水中翼船で、アルミニウム合金製の船体に高速ディーゼルエンジンを2基搭載、推進器にはウォータージェットを採用した。建造は日立造船神奈川工場で行われた。
スーパージェット30(SUPER JET-30)
1993年11月10日 - 高速船「とらいでんとえーす」就航。以後「あるてみす」「あぽろーん」順次就航。
とらいでんとえーす
1993年9月28日竣工、11月10日就航、日立造船神奈川工場建造。
167総トン、全長31.5m、幅9.8m、深さ3.5m、喫水1.9m、ニイガタ16V16FX 2基、ウォータージェット2基、5,000馬力、最高速力時速71km、航海速力時速65km、旅客定員160名
日立造船の開発した水中翼付双胴高速客船「SUPER JET-30」の1番船。ひかり1号の代船として就航。
航路廃止後は係船された後、ベリーズ船籍のTiger3となり、「あるてみす」「あぽろーん」とともに1999年2月23日に神戸港から船積みで中東へ輸出された。
あるてみす「SUPER JET-30」の2番船。輸出時の船名はTiger2。
1994年就航。ひかり2号の代船として就航。
あぽろーん「SUPER JET-30」の3番船。輸出時の船名はTiger4。
スーパージェット40(SUPER JET-40)「シーマックス」
沖縄県石垣市の安栄観光が、2017年から石垣港 - 波照間港航路で「ぱいじま2」として運航されている。テクノスーパーライナー(TSL)
"HAYATE" of Kobe Maritime Museum in Kobe, Hyogo, Japan
15 September 2006
663highland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons実験終了後、神戸海洋博物館で展示されていた「疾風(はやて)」
2016年11月に解体撤去された
疾風(はやて)は実用船の1/6スケールの試験船で、上部船体はアルミ合金で、水中にある下部船体はステンレス鋼でできている。ジェットフォイルとは違い、全重量の半分を下部船体の揚力で支持し、残りの半分は浮力で支持している 。波高6mでも航行できることを目標に設計された。浮力で支持しているが、構造上自己復元力はほとんど働かない。そのため姿勢制御システムが非常に重要であり、疾風はこのシステムを実海域において試験するために作られた。1989年から1992年にかけて開発・設計・製造され、1992年から1994年にかけて試験航行が行われた。試験は主に大阪湾で行われた。高さ6mの波でも40ノットの速度で安定して航行でき、優れた耐航性と操縦性を確認した。また実船を建造するための設計技術があることも実証した。しかし船価や維持費が高く、TSL-F船型の実用化は見送られた。
出典:
Hydrofoil - Wikipedia
Boeing 929 - Wikipedia
Boeing: Historical Snapshot: Jetfoil/Hydrofoil
JETFOIL ミニ百科|川重ジェイ・ピイ・エス株式会社
超高速旅客船 | 船舶 | 川崎重工業株式会社
川崎重工は、1987年に高速旅客船ジェットフォイルの製造・販売権を米国ボーイング社から引き継ぎ、1989年から1995年にかけて神戸工場で15隻を建造しました。その後新造需要は一旦後退しますが、約四半世紀の後に代替需要の時期を迎え2017年に久々の新造発注を得るまで就航船のメンテナンス、改装工事等を継続して関連技術を維持して来ました。
ジェットフォイルは、なぜ、“海を飛ぶ”のか? | 凄いぞコノ船の秘密 | 川崎重工業株式会社
ジェットフォイルについて詳しくは






.jpg)


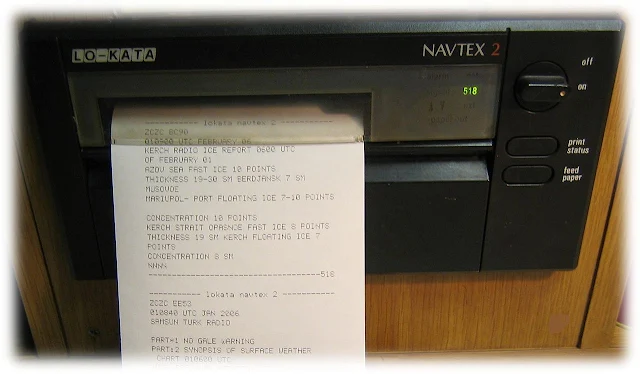
0 件のコメント:
コメントを投稿